全国鯉釣り協会・東日本ブロック/外来生物の取り扱い


このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人及びその協力者の取材情報を基にした部分もあることをご承知おきください。
| 行為の内容 (違反行為) | 必要な対応 (違反にならないための対応法) |
|---|---|
|
釣り大会で釣ったオオクチバスを、釣り 大会後もリリースせず、生きたまま取り 扱うことは違反行為となります。 |
釣ったオオクチバスは、釣り大会終了までにリリース するか、殺処分する。 |
|
釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った 河川・湖沼以外の河川・湖沼に運び移すこ とは違反行為となります。 釣ったオオクチバスを、釣った河川・湖沼 に隣接する湖沼周回道路等を経て検量所に 生きたまま運び移すことは違反行為となり ます。 |
釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す場合は、釣っ たのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性の ある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地の範囲で行う。 (注:湖沼・河川については、たとえ水系でつながって いるものでも、国土地理院発行の地図で名称が付されて いる湖沼・河川ごとに「別の湖沼・河川」とみなします。 また、堰などで魚の動きが制限されている河川について は、その堰などをまたがって「同一性・一体性のある河 川」とはみなしません。) |
|
釣り大会を、複数の湖沼や、河川の一定 水域と言えない範囲で開催し、当該開催 地内で釣ったオオクチバスを生きたまま 運び移すことは違反行為となります。 |
釣り大会の開催は、同一湖沼又は河川の一定水域に限って 行う。 |
|
釣ったオオクチバスを、生きたまま釣っ た河川・湖沼以外の河川・湖沼で放つこ とは違反行為となります。 |
キャッチアンドリリースは、釣ったのと同一湖沼若しくは 釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに 隣接する陸地から行う。 |
|
検量のため、生きたオオクチバスを他者 に引き渡す(例:釣ったオオクチバスを 大会主催者が検量するために、釣り人が 長時間当該オオクチバスを大会主催者に 預ける)ことは違反行為となります。 |
検量は、釣り人自ら行うか、釣り人の「事実上の支配」を 維持した上で大会主催者が行う。 |
|
検量された生きたオオクチバスを、大会 主催者(釣り人以外)が釣った河川・湖 沼に放つことは違反行為となります。 | キャッチアンドリリースは、釣り人自ら行う。 |
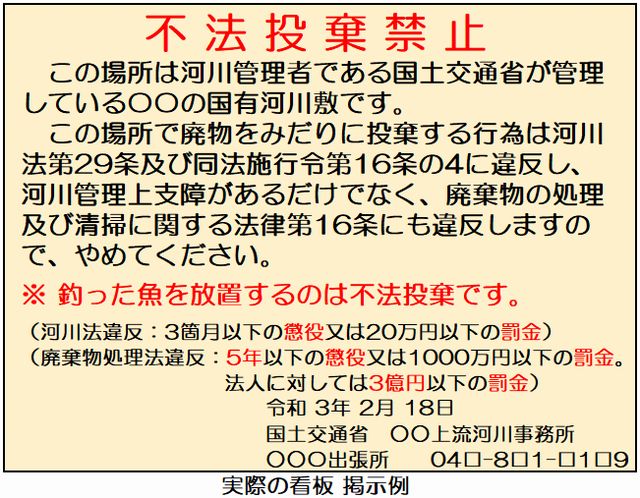
『全国鯉釣り協会東日本ブロック』のPRを目的とする範囲で、東日本ブロックより会報利用による掲載の承諾を受けています。
なお、協会会報の掲載に際しては、翻案/改変せずに掲載することを基本としていますが、レイアウト上からの段落などの改変等がある場合もあります。
この点は、『全国鯉釣り協会東日本ブロック』のPRを目的とする範囲で著作権(財産権)、二次的著作物の創作・利用に関しても黙示の許諾を受けていると判断し行っているものです。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.